フィットネスが趣味のわたし。
7月初旬、エアロビクスのレッスン中に突然ふくらはぎに「ストンと何かが落ちるような感覚」が走りました。
「これってもしかして噂の肉離れ…?」
と不安になり、その場で動くのをやめてドロップアウト。

その場での対応
仲間がすぐに「冷やしたほうがいいよ!」と声をかけてくれて、氷でアイシング。
この迅速な対応のおかげで、大事に至らなかったのかもしれません。
スポーツクラブのスタッフさんから特にアクションがあるわけではなく(もちろんそれが悪いという意味ではなく、クラブの性質上そういうものなんだと思います)、
自分の体は自分で守る知識が必要だな と痛感しました。
幸い、わたしの周りにはスポーツや体の動きに詳しい仲間がたくさん。
肉離れを経験した方やケガに詳しい方が声をかけてくれて、本当に心強かったです。
ひとりだったら不安でパニックになっていたと思います。
診断と治療
翌日整形外科で診察を受けた結果は 筋膜炎。
さらに「1週間は運動禁止」と言い渡されました。
処方されたのは ロキソニンテープ。
これを貼っていたら、痛みは3日ほどで落ち着いていきました。
ただし「動けるようになった=治った」ではないので、しっかり休養を守りました。
回復のためにやったこと
- 冷やす:発症直後は氷でしっかりアイシング
- ロキソニンテープ:処方通りに使用し、炎症と痛みを抑える
- 運動を休む:先生の指示通り、1週間完全に運動ストップ
- フォームローラーでケア:患部ではなく、太ももやお尻を軽くほぐす
- ストレッチ:股関節や腸腰筋を伸ばし、復帰に備える
正直、早く動きたくて仕方がなかったけれど、今回はぐっと我慢して “休む勇気” を持ちました。
ふくらはぎ筋膜炎になった主な原因3つ
① 連日の瞬発系レッスンによる筋肉疲労の蓄積
発症前日にステップやハイインパクトなエアロが連続。ふくらはぎの筋肉が回復しきれず炎症に。跳ぶ・走る動作は特に負担大!
② ミネラル不足(特にマグネシウム・カリウム)
猛暑で発汗量が多く、水や炭酸水だけでは電解質不足に。筋肉の正常な収縮に必要なミネラルが不足すると、痙攣や過緊張→筋膜炎の引き金に。
③ 軽視しがちな“見えない疲労”
普段ケアしていたからこそ「これくらい大丈夫」と思ってしまった小さな疲れ。蓄積されてある日“プチン”と来るのが筋膜炎の怖いところ。
これからの対策3つ
① ミネラル+電解質の積極補給
水分補給は「水+ナトリウム・カリウム・マグネシウム」を意識!
市販の経口補水液やスポドリ、塩レモンウォーターも◎
② 高負荷の日は“回復の計画”もセットに
跳ぶ・走る系の翌日は軽めに/休養日をつくる。
1週間単位で「回復デザイン」するのがカギ。
③ 違和感に気づいたらその場でSTOP
「ヤバいかも」と思った瞬間に止まる勇気。
アイシングやストレッチ、必要なら中断してでも悪化を防ぐ!
思い返してみると
その日は「特に動きすぎた」感覚はなく、いつも通りのつもり。
でも、振り返れば スクワット多めのトレーニングをやった後にエアロ を受けていました。
夏場は思っている以上に筋肉疲労が溜まりやすいのかもしれません。
「普段通りの動き」でも、体が疲れているときは負担になってしまう。
この出来事で、自分の体の声をもっときちんと聞くことの大切さを学びました。
シューズについて
今使っているエアロシューズは、もう3〜4年前に買ったもの。
クッションや安定感も落ちているはずで、それも原因のひとつかもしれません。
次はデザインだけでなく、サポート力や耐久性も重視して選びたい と思います。
わたし調べ:筋膜炎ってどんなもの?
筋膜炎とは、筋肉を包んでいる膜(筋膜)が炎症を起こしてしまう状態。
筋肉そのものの断裂ではないけれど、炎症が強いと痛みで動けなくなることも。
特徴としては
- ふくらはぎなど「よく使う部位」に起こりやすい
- 違和感 → 痛みに変わることもある
- 無理して動くと長引く・再発しやすい
という点があります。
再発防止のために気をつけたいこと
- ウォームアップとストレッチを丁寧に
- シューズの見直し(クッション性・横の安定性のあるもの)
- 疲労の蓄積をためこまない(夏は特に注意)
- 痛みが出たらすぐ休む
- 筋肉の柔軟性アップ(股関節・太もも・お尻)
おわりに
筋膜炎は「ちょっと違和感あるけど大丈夫かな?」と軽く見てしまうような症状なのに、しっかり休まないと治らないし再発しやすい厄介なもの。
今回は仲間の助けもあって大きなケガにならずに済みましたが、同時に「知識」「セルフケア」「靴やトレーニング環境」など、自分でコントロールできる部分を大事にしないといけないなと感じました。
大好きなエアロを長く続けていくために、これからは 体をいたわりつつ、楽しみ続ける工夫 をしていきたいです。

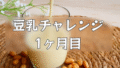
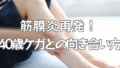
コメント